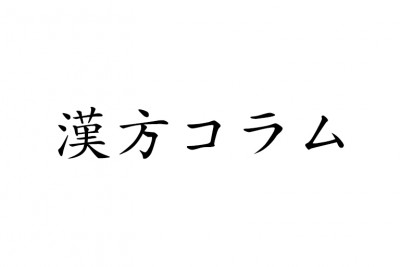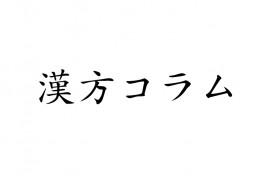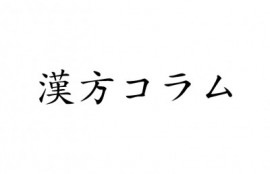“脾”は湿を嫌う
漢方理論では“脾”は湿を嫌うとされ、これからの季節、湿度が高くなるにつれて腸内細菌バランスが悪化しやすくなります。腸内細菌叢の乱れは“後天之本”である“脾”の機能低下につながり、便通のみならず、アレルギー疾患やうつ病、生活習慣病、不妊症など多くの疾患と関連しており、その影響は全身に及びます。
こうしたことから、巷では“腸活”が注目され、ヨーグルトをはじめ食品メーカーなどがこぞって“腸活”をターゲットにした商品を開発していますが、人体には腸内細菌叢を健全に保つための仕組みがいくつか備わっており、現在解明されている腸内細菌に影響する要素をいくつか挙げておきます。
食べもの
腸活に関しては善玉菌のエサとなる食物繊維やオリゴ糖を多く含むものが良いとされています。なかでもキク科の野菜(春菊、レタス、ゴボウ、菊芋など)には水溶性食物繊維であるイヌリンを多く含むものが多いほか、ユリ科の野菜(玉ねぎ、にんにく、ニラ、アスパラガスなど)はオリゴ糖を多く含む傾向にあります。因みに健脾作用の代表的な生薬である白朮もキク科です。また、芋類や豆類、発酵食品なども腸活にプラスになります。
反対に、腸内細菌叢を悪化させるものとしては、動物性脂肪が代表的なものですが、現代においては食品添加物や人工甘味料なども挙げられます。また、いくら腸活になる食べ物でも冷たいものや夜遅い時間の食事はNGです。
口腔環境
口腔内にも無数の細菌が生息していますが、悪玉菌が増えると歯周病の原因になるばかりか、消化管を通って腸内に達することで腸内細菌叢が乱れます。特に、フソバクテリウム・ヌクレアタム菌は大腸がんとの関連性が強く、大腸がんの4割以上で検出されています。また、歯周病などによってよく噛めない状態になると食品の消化に支障をきたし腸内細菌叢にも悪影響が及びます。
胃酸
胃酸の出が悪いと、胃に入ってきた口腔内の悪玉菌や食品に含まれる有害な菌を殺菌できなくなって腸内細菌叢に悪影響を与えます。因みに、PPIなど強力に胃酸を止める薬を常用することは食品中のミネラルの吸収に悪影響を与えるほか、食中毒や腸管感染症のリスクが高くなります。
α-ディフェンシン
小腸のパネト細胞は、乳酸菌などの常在菌には作用せず、病原菌に対してのみ殺菌作用を有するα-ディフェンシンという抗菌ペプチドを分泌することによって腸内細菌叢を制御しています。因みにα-ディフェンシンに関しては、ストレスや老化、睡眠不足によって分泌量が低下する反面、味噌などに含まれる麹菌の作用で生じるピログルタミルペプチドは微量でもα-ディフェンシンの分泌を増やし、ラットを用いた実験で高脂肪食によって誘発される腸内細菌叢の乱れを改善したことが報告されています(※1)。
IgA抗体
腸管内に分泌されるIgA抗体は、腸管内で病原菌やその毒素と結合して無毒化するだけでなく、粘膜固有層内に侵入した病原体と結合して体外に排出し、有用な菌種に対しては腸管の粘液層への定着を促進することで腸内細菌叢を制御しています。因みに、虫垂に存在するリンパ組織がIgA産生に重要な役割を担っており、虫垂を切除することは腸内細菌叢にダメージを与えます。また、ストレスによってもIgAの分泌量は減少します。
以上みてきたように、人体には腸内細菌叢を制御する様々な仕組みが存在しており、霊芝に含まれるガノデリン酸は用量依存的に腸管におけるIgAの分泌および、パネト細胞からの抗菌ペプチドであるαディフェンシンの分泌を増加させることが知られています。また、中国における認知症やパーキンソン病などに対する鹿茸の有効性に関する論文では、作用機序については不明ながら、鹿茸には腸内細菌叢を改善させる作用があることが指摘されていますが、これは腸内細菌叢を制御する様々な人体の機能を活性化した結果ではないかと思います。
(※1)
https://repository.kulib.kyotou.ac.jp/dspace/bitstream/2433/253335/1/ynogk02403.pdf