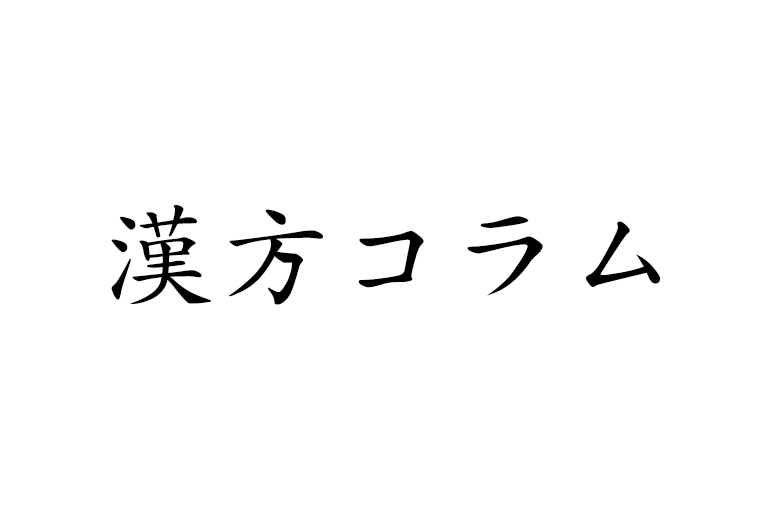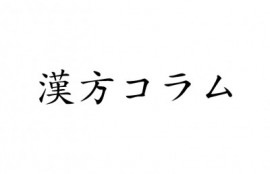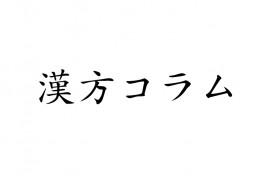機械論的生命観
薬局の店頭で患者さんと話をしていると、血圧を一回測っただけで数値が高ければすぐに高血圧であると思いこんだり、健康診断で検査データが正常値からはみ出したりすると心配でしかたがないという方は多いです。また、高血圧と診断され降圧剤を服用して血圧が正常値になったら、自分のからだは“正常”だと安心してしまう方もよく見かけます。こういった考えの背景には本人も自覚はしていないでしょうが、人体を機械のように考える機械論的生命観があるように思います。実際に日本の健康診断や医療現場では異常値を見つけ出すための検査が中心で、異常値が見つかれば対症療法薬で異常値を正常値にすることが最終目的と錯覚させられるような現状では、そういった風潮となるのもしかたのないことかもしれません。また、人体を臓器や組織などに細かく分けて観察する事で西洋医学が発展してきたことで、何となく人体を機械のようなパーツの集合体と見なすようになったのかもしれません。
ところが、以前このコラムでも紹介したシェーンハイマーの実験結果や、西洋医学が分子生物学とよばれるような領域まで踏み込んだときに、人体は決して機械のようなものではなく、ミクロの世界では動的平衡とよばれるようなダイナミックな変化を絶えず繰り返していることや、自然界の一日のリズムに合わせてホルモンの分泌や体温の調整などを行っていること(概日リズム)などが明らかになりました。結局、生体を構成する“物質”よりも生命を維持している“事象”にこそ生命の本質があり、その“事象”は絶えず変化しながら一定のリズムを刻んでいるという、極めて東洋的な生命観にたどり着いたわけです。
生命と“ゆらぎ”
さて、機械論的生命観とはかけ離れた分野として近年注目されているのが、生体のもつ“ゆらぎ”です。例えば、心拍や血圧や体温といったバイタルサインに関しても機械論的な生命観からは規則正しく一定である方がよさそうなものですが、健常者では一見規則正しそうに見えても、その値は微妙に変化しつつゆらいでおり、ゆらぎが少ない方が高齢や病的状態であることがわかっています。関西学院大学名誉教授の雄山真弓博士によれば、赤外線センサーを用いて指先の毛細血管を流れるヘモグロビンの増減(指先容積脈波)を測定し、特殊な数式を用いてアトラクターと呼ばれる図形に変換すると、規則性をもった楕円のような形状を示し、健常者ほど“ゆらぎ”、即ち楕円を構成する軌道の幅が太くなり、うつ病患者や認知症の老人では細くなるそうです。
また、最先端の分子生物学の分野においても、細胞レベルでの“ゆらぎ”は注目されています。この分野の研究はまだ始まったばかりで、同一の遺伝子を持つ細胞集団においても、それぞれが異なる“ゆらぎ”方をしている理由や、個々の細胞はゆらいでいても、生物全体としての秩序を保っているのは何故なのかといった事に関して研究が進められています。ただ、少なくとも、生体内の分子の動きに関して、周囲からの熱エネルギーをはじめとする様々なノイズに対応するために“ゆらぎ”が存在しており、その“ゆらぎ”の存在こそが生体内の円滑な化学反応の鍵を握っていると考えられています。
ところで、この“ゆらぎ”という言葉に関して、江戸時代の剣豪宮本武蔵が「五輪書」の中で、兵法の心得として心がゆらいでいる状態であることが肝要であり、心が“いつく(こり固まる)”ことを避けるべきと記しています。要するに細胞レベルでも生命体全体としても外部からのストレスに対応する為には“ゆらぎ”の存在こそが重要であるということのようです。
この“ゆらぎ”について漢方的に考えた場合、気の巡りが滞りなくスムーズである状態が適度にゆらいでいると考えられます。そう考えると、ストレスにより乱れた気の巡りを正常な状態に戻してくれる気つけ薬とは、ストレスで小さくなった“ゆらぎ”を回復させるもので、精神的な部分のみならず生命活動そのものを円滑にする効果があると思います。