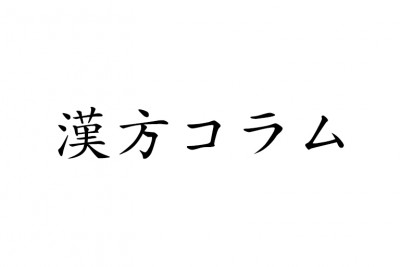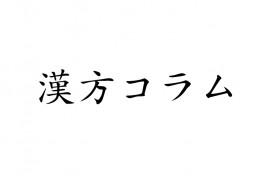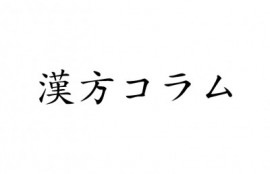五臓との関係
近年、人体における腸内細菌の役割について研究が進んでいます。腸内細菌叢(細菌だけでなく、ウイルスや真菌なども含めてマイクロバイオータもしくはマイクロバイオームとよばれることが増えています)の役割に関しては、漢方的には“後天之本”である“脾”の機能面と重なります。もともと五臓の中でも“脾”は中心かつ一段高いところにあって、その周囲を“肝”“心”“肺”“腎”が囲みつつ、それぞれが“脾”からの影響を受けているとする概念(土王説)がありますが、西洋医学的にも腸内細菌叢が様々な内臓と情報をやりとりしていることが明らかになってきています。
腸肝相関
肝臓に流れ込む血液の7割以上は腸などの消化管から門脈を通じて送り込まれますが、腸内細菌叢の乱れからリーキーガット(腸の粘膜のバリア機能の破綻から腸管内の物質が血液中に漏れ出す)状態になると肝臓に腸管内の病原体や異物が運び込まれることから肝機能の低下につながります(脂肪肝も過食などが原因で腸内細菌叢が乱れることで、有害なエンドトキシンなどが肝臓に送られ肝臓の炎症を引き起こしています)。また、肝臓では胆汁酸がつくられ、胆嚢から消化管に分泌されることで脂肪分の消化を助けています。ただし、肥満などでは腸内細菌叢が乱れて、大腸にまで届いた一次胆汁酸から変換される二次胆汁酸が有意に増加し、二次胆汁酸が肝臓に輸送されることで肝臓がんのリスクが高くなることが動物実験で確かめられています。
腸脳相関
腸と脳(五臓では主に“心”)との関係は比較的古くから解明されており、「脳は、視床下部から分泌するホルモンや遠心性迷走神経を介して腸の機能を調節していて、腸は、腸内分泌細胞から分泌する消化管ホルモンや腸から脳へつながっている求心性迷走神経を介して脳へ情報を伝えている(※1)」ことがわかっています。このため腸内細菌叢の乱れはストレス性の症状から発達障害、うつ病あるいは認知症にいたるまで影響するとともに精神的なストレスは腸内細菌叢を悪化させます。
腸肺相関
これまで無菌とされていた肺にも細菌叢が存在することが明らかになっています。また、腸内細菌が食物繊維をもとに作り出す短鎖脂肪酸のひとつである酢酸が血液を通じて肺の上皮細胞に存在する短鎖脂肪酸受容体を活性化して抗ウイルス作用のある1型インターフェロンの産生を増強し、感染症における肺炎の症状を軽減することも報告されています。実際に新型コロナ流行時、日ごろから発酵野菜をよく食べている人は新型コロナ感染症での死亡率が低いことがフランスで発表されています(※2)。
腸腎相関
腸内細菌叢が乱れてリーキーガット状態になることで、インドキシル硫酸などの尿毒素とよばれる成分が血液を通じて腎臓に運ばれることで腎機能が低下するほか、昨年の8月に慶應義塾大学などの研究チームから、リーキーガットによって腸管内のIgAが腎臓の糸球体に沈着することが指定難病のIgA腎症の原因であると発表されています(※3)。また、金沢大学などの研究で、腸内細菌由来のD型アミノ酸であるD-セリンに腎臓保護作用のあることも発表されています(※4)
あと漢方では“腎”に分類される生殖器官に関しても、腸内細菌叢の良し悪しは、子宮や卵巣の状態に影響することがわかっており、腸内細菌叢に問題があると不妊症や流産、子宮内膜症、膣カンジダ症のリスクが高くなることが知られているほか、精子の形成や運動性に対しても悪影響を与えることも報告されています。
以上みてきた以外にも、腸内細菌叢の状態はアレルギー疾患や2型糖尿病、高尿酸血症、高脂血症との関連性も認められており、その影響は全身に及びます。正に“脾は後天之本”であるといえます。
(※1)「腸と脳の科学」坪井貴司著p53~p54
(※2)https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/32762135/
「Cabbage and fermented vegetables: From death rate heterogeneity in countries to candidates for mitigation strategies of severe COVID-19」
(※3)https://www.keio.ac.jp/ja/press-releases/2024/8/5/28-161021/
(※4)https://www.kanazawa-u.ac.jp/rd/61999/